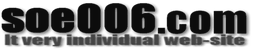第一次大戦の従軍体験を元にエリッヒ・マリア・レマルクが書いた小説「西部戦線異状なし」が映画化されたのは1930年。それから56年後、オリヴァー・ストーンがベトナム戦争体験を元に脚本を書き監督したのが「プラトーン」。
両作に共通しているのは、誰ひとりとして「自国の勝利」とか「栄誉の勲章」などではなく、「とにかく戦場で生き残るため」に戦っていた、ということ。前線で戦っている兵士たちの思いは、半世紀の時間を経ても、何ひとつ変わっていなかった。

戦争映画としては低予算(600万ドル)だが、オール現地ロケ(フィリピン)で、服装や装備にしても、手抜かりない迫真性が感じられる。映像は即物的なカットの積み重ねで、無理に面白くしようと作為的にしていない。ドキュメンタリー性に重きをおいて無骨に撮る。こうした映画作りがオリヴァー・ストーンの真骨頂。一遍のユーモアもなく、娯楽性に乏しいので見ていてすごく疲れる映画。名作ではある。
アカデミー賞というのはハリウッド業界人がでっちあげた茶番だと思っているのだが、「アカデミー作品賞」として記録に残ることで、若い世代がこの映画を観る機会になるのであれば、結果として「プラトーン」の受賞は意義があったと思う。
なぜなら、そんな映画今更見たって意味ないよ、見る価値ないよ、みたいな政治的工作が(やんわりと密かに)今後、あるかも知れないから。
出演者全員が兵隊になりきった演技をみせている。ベトナム戦争の退役軍人をアドヴァイザーに迎え、撮影前に現地で2週間の訓練を受けた成果だろう。

トム・ベレンジャー、ウィレム・デフォー、チャーリー・シーン、フォレスト・ウィテカー、ジョニー・デップなど、このあと名をあげたスターもいる。
ケヴィン・ディロン(マット・ディロンの弟)、フランチェスコ・クイン(アンソニー・クインの息子)、ジョン・C・マッギンレー、キース・デヴィッドあたりは、脇役で地味に俳優を続けている。
終盤、敵の総攻撃を受ける駐屯地の場面では監督も特別出演。
司令部の壕ごとふっ飛ばされている。

いちばん強く印象に残ったのは、部隊が焼き払う農村の人々。片脚を失っている男を機関銃で脅して踊らせる場面は、目を背けたくなる。
点