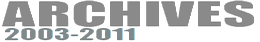サン=サーンス:組曲「動物の謝肉祭」
August 28, 2007
いきなりですが……
前回「クラシック de 枕草子(春):サン=サーンス」の訂正です。
サン=サーンスのディスクは1枚も持っていないと書きましたが、実は1枚だけ持っていました。オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団の「動物の謝肉祭」(CBS/Sony)。
サーバー移転の準備で過去の日記を整理していたら、2006年5月5日「こどもの日」に紹介しておりましたです。
まあ、身銭を切って購入したのに持っていたことさえ忘却してしまうくらい稀薄な作曲家だったのですね、サン=サーンスは。
このオーマンディ&フィラデルフィア盤もプロコフィエフの「ピーターと狼」とのカップリングだし、やっぱり(や、巴里)、サン=サーンスは子ども向け、色物(いろもの)としてしか認識していなかったんですよ。
子どもの頃に聴いたときも、動物の鳴き声なんぞを楽器で模写しているだけの冗談音楽、底の浅い、傾聴に値しない音楽と断定してたくらいで……いやもう、小学生のクセになんて生意気なガキなんでしょう。我がことながら、アタマを引っぱたいてやりたいくらいです。
で、このたび「のだめカンタービレ」で流用された「動物の謝肉祭」の第7曲「水族館」を聴くためだけに購入したのが、こちらのディスク。2枚組、税込み1500円也。
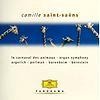 |
サン=サーンス作品集 DGパノラマ・シリーズ
1. 交響曲第3番ハ短調op.78「オルガン付き」 Deutsche Grammophon (2枚組) |
このCDに収録されている個々の楽曲については、このあと逐次紹介していきます。
今回は「動物の謝肉祭」だけにスポットをあてます。
上記DGパノラマ・シリーズに収録されている「動物の謝肉祭」はPhilipsレーベルからリリースされていた、(オリジナル編成の)室内楽版。こちらがその原盤です。
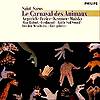 |
サン=サーンス:組曲「動物の謝肉祭」マルタ・アルゲリッチ、ネルソン・フレイレ(p)、ギドン・クレーメル、イザベル・ファン・クーレン(vn)、タベア・ツィンマーマン(va)、ミッシャ・マイスキー(vc)、ゲオルグ・ヘルトナーゲル(cb)、イレーナ・グラフェナウアー(fl)、エドゥアルト・ブルンナー(cl)、他
1. サン=サーンス:組曲「動物の謝肉祭」 1985年 デジタル録音 Philips |
個性派アルゲリッチ以下、ヴァイオリンのギドン・クレーメルなど錚々たるメンバーが勢揃い。ユーモアたっぷり、和気藹々の雰囲気のなか、それぞれが自慢の技を惜しみなく披露。室内楽版「動物の謝肉祭」の定番アルバムであります。
この演奏で、あらためて全曲を聴いて、目から鱗。
「動物の謝肉祭」って、シニカルな大人の視線で音楽を捉えた、諧謔趣味の音楽だったのですね!
ガイド書や音楽鑑賞の手引きなど、いろんなところで「動物の謝肉祭」がサン=サーンスの代表曲として紹介されているのは、実に不幸なことであります。
もちろん、第13曲「白鳥」はチェロ奏者ならば誰でも一度は弾くであろう流麗な曲で、サン=サーンスの名前も知らないような人でも、幾度となく耳にしたことのあるポピュラー名曲ですが、この組曲は、普段の(シリアスな)音楽活動を離れて、休日を楽しく過ごそうといった感じの、音楽家たちの遊び、余興・余技なんです。
団令子さんが亡くなったとき、ワイドショーなどでしきりに「黒澤明監督の『椿三十郎』や『赤ひげ』に出演していた団令子」と紹介していましたが、黒澤映画での団令子は脇役だったし、巨匠監督との仕事なら小津安二郎の『小早川家の秋』にだって出演していたし、それらは普段演じていたキャラクターとは異なる特別な役柄だったわけで、彼女がもっとも本領発揮していたのは、『お姐ちゃん』シリーズ等の東宝プログラムピクチャアだったでしょう?
黒澤映画だけ観たんじゃ、団令子が1960年代に東宝のスター女優だった理由は、分かりっこありませんよ。
紹介する際に誰もが知っている作品を引き合いに出すのは仕方ないこととしても、それを代表作であるかのように喧伝するのはどうかと思いますです。
もし私が上記2枚組パノラマ・シリーズに出会ってなかったら、死ぬまでサン=サーンスを誤解したままだったかも知れませんね。
これは、本当に恐ろしいことです。
組曲「動物の謝肉祭」は、1886年(サン=サーンスが51歳のとき)に作曲されています。
楽器編成は……ピアノ2、ヴァイオリン2、ヴィオラ、チェロ、コントラバス、フルート、ピッコロ、クラリネット、木琴、グラス・ハーモニカ。
同年3月9日、友人のチェリスト、シャルル・ルブークが主催するマルディ・グラ(謝肉祭の最終日)の音楽会にて初演。
初演では、2台ピアノのうち1台を作曲家自身が受け持ち(サン=サーンスはかなり優秀なピアニストでもあったのです)、チェロはもちろん友人のルブーク。
作曲を依頼したチェリストのために、最高の聞かせどころ(第13曲の「白鳥」)を用意しています。気むずかしく敵の多いサン=サーンスでしたが、才能を認めた音楽家への友情は篤かったのでしょう。
お祭りの余興として作った楽曲でもあり、また他の作曲家の作品を引用している(というよりは茶化してる)などの理由から、生前は楽譜出版を許可しなかったサン=サーンスですが、このチェリストのための1曲だけは出版を許可しています。後年に残る名曲だと、本人も自信があったのでしょう。
事実、21世紀の今日でも、頻繁に演奏され続けております。
グラス・ハーモニカというのは、大小のガラスのコップに水を入れて、その水の量を加減して音階を作る楽器でしょうか? むかし浅草演芸ホールでそういうのを演奏する芸人さんを見たことがあります。第7曲の「水族館」で、神秘的な音色を聞かせるのがそれですが……ほとんどの演奏で、グロッケンシュピールまたはチェレスタで代用されてるみたいです。上記Philips盤でもグロッケンで演奏されています。
一度、グラス・ハーモニカで聞いてみたいですね。
第1曲「序奏と獅子王の行進」
2台ピアノと弦楽合奏で、アンダンテ・マエストーソ(歩くような速度で荘厳に)の序奏。
続いてピアノが行進曲のリズムを刻み、低弦による百獣の王ライオンが堂々の入場。ピアノの低域がおどろおどろしく咆吼。主旋律をピアノが引き継ぐと、ライオンの足取りが軽くなります。
第2曲「雄鶏と雌鶏」
ピアノと弦楽器で雄鶏、クラリネットで雌鶏の鳴き声を模した曲。
ココココ、コケェー、ココココ、コケェー、やかましいです。
第3曲「驢馬」
2台ピアノが目まぐるしく音階を上下させ、野性のロバが激しく跳ねまわる様子を描写。
第4曲「亀」
反復するピアノのリズムに、弦楽器がのったりのったり鈍重に歩むカメを描写。こいつはお祭の露店なんかで売っているミドリガメじゃなくて、ウミガメやゾウガメのような大型種ですね。
カメの旋律は、オッフェンバックの「天国と地獄(地獄のオルフェウス)」から、有名なカン・カンのメロディを、おそーく、おそーくしたもの。ご存知のように、この元メロディは、快活にダイナミックにテキパキと演奏されてこその曲。その逆手をとって、鈍く重く演奏することでまったく反対の印象を作ってしまったわけです。編曲の面白さですね。
そういう分かり易さが、小学校で教材にされている理由でもあるんでしょう。
同じメロディをテンポと楽器を変えて、あるときは激しくダイナミックに、あるときは甘く切なく、そしてあるときは重く悲痛な雰囲気で、といったやり口は、映画音楽を聞き慣れている人には、ダカラナンヤネンって感じだろうけど。
第5曲「象」
第2ピアノによるワルツのリズムにのって、コントラバスの象。
象の旋律は、ベルリオーズの「ファウストの劫罰」とメンデルスゾーンの「真夏の夜の夢」の一節から作られています。
第6曲「カンガルー」
2台ピアノで飛び跳ねるカンガルーを描写。
テンポに自由な変化をつけて、動物の気ままに気まぐれな感じを出しています。
第7曲「水族館」
水槽の中で神秘的に揺れる水藻(ピアノ)と、漂うように泳ぐ魚(フルート、グラス・ハーモニカ)。
ミステリアスな雰囲気が醸し出されている曲。
「のだめカンタービレ」では、催眠術の場面や、練習中に倒れた千秋真一が宇宙アメを吐き出す場面に流用されていました。
第8曲「耳の長い登場人物」
耳の長い登場人物とはロバのことで、2部のヴァイオリンが交互にブギャーと啼いています。
と同時に……耳の長い登場人物とは、その大きな耳で耳賢く音楽を聞き、愚にもつかぬ批評を口にしている評論家たちのことでもあるらしいです。サン=サーンスの皮肉が出た、耳障りな曲。
第9曲「森の奥のカッコウ」
ピアノが描写する仄暗い森の奥から、クラリネットのカッコウの声が聞こえてきます。煩かったロバ(耳の長い登場人物)の後だけに、その静かな佇まいが対照的かつ効果的。
第10曲「大きな鳥籠」
これはたぶん動物園にあるような、大きな檻のような鳥籠だと思います。弦楽器の細かいトレモロ、フルート、ピアノなど、たくさんの種類と数の鳥たちが飛び交っています。
第11曲「ピアニスト」
第8曲「耳の長い登場人物」と同様、サン=サーンスの皮肉がたっぷり込められた愉快な曲。私はこの曲を聴いて、「動物の謝肉祭」が単純に動物の生態を模した子ども向けの音楽ではなかったことに気づきました。
ちなみに、この曲は、私が演奏できる唯一のピアノ曲で、たとえカーネギー・ホールの大舞台であったとしても、誰よりも的確に、作曲者が意図したとおり忠実に、弾ける自信があります。
もっとも私が弾いてもナンセンス。アルゲリッチのような名人が楽譜の指示通りに弾くから面白いのです。
サン=サーンスのユーモアが続きます。
12曲目は、なんと化石です。
第12曲「化石」
まず最初に自作の交響詩「死の舞踏」からのメロディを木琴で。
この交響詩は、墓場に眠っていた骸骨が真夜中に蘇って朝まで踊る、という内容で、骨=化石ということです。
ところが曲はそれで終わりではなく、続いて「キラキラ星」、更にクラリネットがロッシーニの「セヴィリャの理髪師」からの一節を演奏……つまり、過去の音楽=化石という趣向なのでした。
第13曲「白鳥」
水面をゆっくりと滑るように、優雅に泳ぐ白鳥をチェロの独奏で。
ソフト・フォーカスの映像が目に浮かぶ名曲中の名曲。このポピュラリティーこそがサン=サーンスの魅力であります。分かり易く(耳に馴染みやすいと言い換えた方がより的確かな?)、美しいメロディ。私が長い間、子ども向けの色物作曲家と思い違いしていたサン=サーンスは、実は、たいへんなメロディメーカーなのでありました。
第14曲「フィナーレ」
モルト・アレグロの快活なテンポで、これまで紹介されてきた動物たちがゾロゾロ出てきます。
その構成の巧さ。楽器の特性や音色を熟知した、サン=サーンスならではの見事なフィナーレに拍手喝采。
50歳を過ぎたオッサンが、気の置けない仲間たちを集め、童心に還って遊んでいる。
これが組曲「動物の謝肉祭」の正体だったんですね。
別に子どもたちを喜ばそうとして作った曲じゃなかったんです。
これまで聴いていたオーマンディ&フィラデルフィア盤では、それがピンときませんでした。アルゲリッチ他による室内楽版を聴いて、はじめて分かりました。フィーリングで。
ちなみにフィーリングというのは、その人間の持っている知識と経験の蓄積によって知覚される超絶感覚でありまして、「なんとなく」とか「雰囲気で」とか口では言ってますけど、実に幽玄秘奥なるものであります。
子ども時代に感じることができなかったものが、歳をくうとスンナリ自然に分かるようになる。よく「子どもの感性」とか耳にしますけど、あんなのは動物的本能による勘であって、犬や猫と同じもの。年寄りほどフィーリングは豊かなのであります。
フィーリングをバカにしちゃイカンです。
この組曲を愉しむのには、やはり室内楽編成がよいと思いますが、世間にはオーケストラ版のディスクも多く出回っています。
オーケストラ版での演奏では、ジョルジュ・プレートル指揮パリ音楽院管弦楽団が定番のようですね。
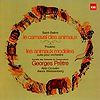 |
サン=サーンス:組曲「動物の謝肉祭」アルド・チッコリーニ、アレクシス・ワイセンベルク(p)、ミシェル・デボスト(fl)、ロベール・コルディエ(vc)、他
ジョルジュ・プレートル指揮
1. サン=サーンス:組曲「動物の謝肉祭」 1965年 ステレオ録音 EMI |
「動物の謝肉祭」は(超個人的に)アルゲリッチ他によるPhilips盤だけで充分だったのですが、(第3番以外の)ヴァイオリン協奏曲や(第2番以外の)ピアノ協奏曲も聴きたくなって、仏EMIから出ている5枚組ボックスセットを買ったら、このプレートル&パリ管の「動物の謝肉祭」も収録されていました。
ピアノ協奏曲全集も録音しているサン=サーンス弾きの第一人者チッコリーニをはじめ、名ソリストたちを揃えたパリ管弦楽団全盛期の演奏です。フランス的な色彩と雰囲気のよさ、ユーモアもたっぷりあって、オーケストラ版「動物の謝肉祭」の定番アルバムなのも頷けます。
オーケストラ版の演奏をもう一つ。
こちらも交響曲第3番「オルガン付き」を目当てに買ったら、「動物の謝肉祭」がおまけで入っていました。
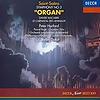 |
サン=サーンス:交響曲第3番「オルガン付き」
ピーター・ハーフォード(オルガン)
交響詩「死の舞踏」
組曲「動物の謝肉祭」 Decca |
この「動物の謝肉祭」はダメですね。
デッカのデジタル録音は素晴らしく、サウンドは綺麗で、個々の楽器は明瞭に聞こえてきますけど、肝心の演奏が……ヘタクソに弾けって楽譜に指示がある第11曲「ピアニスト」に顕著ですが、これは、遊びというものをまったく理解していない演奏ですね。
パスカル・ロジェが真面目なのか、デュトワが嫌ったのか知りませんけど、先のアルゲリッチやチッコリーニと比べたら一目瞭然。もしこちらがパノラマ・シリーズに収録されていたら、いまでも「動物の謝肉祭」は、子ども向けの色物音楽だと思い続けていたことでしょう。
そもそもデュトワという指揮者は、個性が稀薄というか、実体がないというか、独自の解釈を施さない人なので、私に合わないのです。デュトワ人気も、デッカの優秀録音に助けられているところが大きいのではないでしょうか。過大評価されていると思いますよ。
もっとも、そういう独特のカラーがないところが楽譜に忠実な演奏で良いのだ、という人もいらっしゃるみたいですけど。
(このディスクに収録されている交響曲第3番については、また機会をあらためて書きます)
追記:
サン=サーンスの録音盤は、その膨大な作品数に比べて少なく、比較的録音の多い「動物の謝肉祭」と交響曲第3番「オルガン付き」以外の楽曲は、かなりマイナーなのが現状。
いちいちディスクを探し回るのが面倒だったので、エイヤーと買っちゃったのが、フランスのEMIから出ていた5枚組ボックスセット。
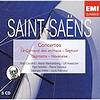 |
サン=サーンス:Pf協奏曲&Vn協奏曲全集
アルド・チッコリーニ (ピアノ) EMI (5枚組ボックス)輸入盤 |
ピアノ協奏曲全曲(第1番〜第5番)、ヴァイオリン協奏曲全曲(第1番〜第3番)の他に、上記プレートル&パリ管による「動物の謝肉祭」や、チェロ協奏曲第1番、七重奏曲変ホ長調、ピアノ五重奏曲イ短調、ワルツ形式の練習曲(ピアノ独奏)、「序奏とロンド・カプリチオーソ」や「ハバネラ」などのヴァイオリンと管弦楽のための小曲(9曲)が約6時間30分収録されていて、交響曲とオペラ以外のサン=サーンスは一網打尽!……とはいかないほど作品数が多い作曲家ですが。
とりあえずどんな作品傾向なのか、手っ取り早く知るには良い買い物でした。