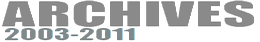サン=サーンス:交響詩「死の舞踏」 作品40
September 14, 2007
ジグ、ジグ、ジグ。
踵(かかと)で拍子をとりながら、死神は叩く墓の石。
真夜中に死神が弾く、踊りの調べ、
ジグ、ジグ、ジグと、ヴィオロンで。
暗い夜に冬のつむじ風が叫び、菩提樹から高まる呻き声。
蒼白き骸骨が暗闇をよこぎり、大きな経帷子をまとって走り踊る。
ジグ、ジグ、ジグ、人はみな怯え、震えあがるだろう、
ダンサーたちの、骨がかち合う音を耳にすれば。
静まれ! 踊りは突然に終わり、彼らは押し合いながら逃げてゆく。
暁の鶏が鳴いたのだ。
(交響詩「死の舞踏」のスコアに引用されたアンリ・カザリスの詩より)
交響詩「死の舞踏」(op.40)は、フランスの詩人アンリ・カザルスの奇怪な詩に暗示された作品で、死神が奏でるヴァイオリンに導かれ、墓場で踊り狂う骸骨の様子をリアリスティックに描写。サン=サーンスの巧みな管弦楽法が十二分に発揮された人気曲です。
1874年に書かれ、翌1875年1月、パリのシャトレ劇場にて、エドゥアル・コロンヌ指揮の管弦楽団により初演。曲はモンティニ・ルモーリ夫人に献呈されました。
楽器編成は……独奏ヴァイオリン、ピッコロ、フルート2、オーボエ2、クラリネット2、ファゴット2、ホルン4、トランペット2、トロンボーン3、チューバ、木琴、ティンパニ3、トライアングル、シンバル、大太鼓、ハープ、弦5部。
独奏ヴァイオリンはト・ニ・イ・変ホの特殊な調弦を指定。
演奏時間は約7分。
最初にハープのニ音が12回繰り返され、真夜中の到来を告げます。死神が現れ、特殊調弦された奇妙な音色のヴァイオリンでワルツを奏で、この呼びかけによって墓石の下から骸骨たちが蘇ります。
フルートで演奏される第1主題は、中世に作られた聖歌「怒りの日 ディエス・イレ」の旋律を変化させたもの。この旋律を用いた楽曲は、ベルリオーズの「幻想交響曲」やラフマニノフの「パガニーニの主題による狂詩曲」などいっぱいありますね。サン=サーンスは、交響曲第3番「オルガン付き」でも重要なモチーフ(循環主題)として使用していました。
第1主題が弦楽器で繰り返されたあと、不気味な音色の独奏ヴァイオリンが、哀愁ただよう第2主題を提示。第1主題と第2主題は様々に展開しながら交互に繰り返され、骸骨たちの饗宴はどんどん勢いを増していきます。
いったん独奏ヴァイオリンで沈静化したあと、弦楽器の第1主題とトロンボーンによる第2主題がフォルテシモで同時に現れ、宴は一気に盛り上がり、テンポアップ、最高潮に達します。
オーボエが鶏の鳴き声で朝を告げると、骸骨たちは名残惜しそうな素振りを見せながら、土のなかに戻っていきます。
ムソルグスキーの「禿山の一夜」と同じようなストーリーですが、曲の表情はぜんぜん違っていて、比較して聴くと面白いです。
「禿山の一夜」が踏みつけつけるような和音連打のリズムでロシア風なのに対し、「死の舞踏」はパリジャンらしく華麗にワルツ。
はっきりと異なるのは、朝の到来で静謐な世界が取り戻される「禿山の一夜」に対し、「死の舞踏」のコーダでは、地下に還ってゆく骸骨の一抹の寂しさ、哀感が表現されているところでしょう。サン=サーンスは、一夜の宴に饗する骸骨の視点で書いていたんですね。
管弦楽法の達人というと、「禿山の一夜」の管弦楽版を書いたリムスキー=コルサコフと、「展覧会の絵」の管弦楽版を書いたモーリス・ラヴェルの名前がよく挙がりますが、サン=サーンスも2人に劣らない、凄い腕前を持っています。
名人級のピアニストでありながら、フランス最高峰のオルガニストでもあり、魅力的なメロディを奔出する作曲家で、しかも管弦楽の達人でもあるなんて……にわかに信じがたいことですが、天才なのだから仕方ないですね。
カミーユ・サン=サーンスは、その生涯に4つの交響詩(詩的理念を標題とする管弦楽作品)を書いています。
作曲年代順に……
交響詩「オンファールの糸車」(op.31) 1871年
交響詩「フェアトン」(op.39) 1873年
交響詩「死の舞踏」(op.40) 1874年
交響詩「ヘラクレスの青年時代」(op.50) 1877年
最も演奏される機会が多いのは「死の舞踏」で、次いで「オンファールの糸車」。「フェアトン」と「ヘラクレスの青年時代」は滅多に見かけません。
「のだめカンタービレ」でにわかクラシック愛好家となった私を、超個人的にサン=サーンスの世界へと案内してくれたグラモフォン・パノラマ・シリーズにも、「死の舞踏」と「オンファールの糸車」の2曲が収録されていました。
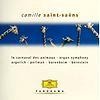 |
サン=サーンス作品集 DGパノラマ・シリーズ
1. 交響曲第3番ハ短調op.78「オルガン付き」 Deutsche Grammophon (2枚組) |
「死の舞踏」はダニエル・バレンボイム指揮パリ管弦楽団(1980年10月録音)、「オンファールの糸車」はレナード・バーンスタイン指揮フランス国立管弦楽団(1981年11月録音)による演奏です。
このDGパノラマ盤には、バレンボイム指揮パリ管弦楽団による、歌劇「サムソンとデリラ」からの舞曲「バッカナール」も収録されています。
サン=サーンスは13のオペラ作品を書いていますが、そのほとんどが現在では上演されていません。日本を舞台にしている「黄色い王妃」(op.30)とか観てみたいものですが……唯一いまでも上演機会のあるオペラが、旧約聖書にもとづく壮大なスペクタクル「サムソンとデリラ」(op.47)。
「バッカナール」は、妖女デリラを餌に色仕掛けでサムソンを捕らえたペリシテ人が、その成果を祝って踊るエキゾチックかつダイナミックなバレエ音楽。バッカナールというのは、「馬鹿な奴」という意味ではなく、酒の神バッカスに捧げる踊りってことであります。
血湧き肉躍るリズムの饗宴。豪快で勇壮なテーマ・メロディ。多彩な楽器が入り乱れ、打楽器群が炸裂。クライマックスのティンパニ猛打に体温上昇間違いなし! ハンス・ジマー系のアクション映画音楽が好きな人は、これはハマっちゃうでしょう。
この舞曲はコンサートでも単独で演奏されることが多く、フランス管弦楽曲集などの企画盤や、交響曲などの余白にオマケとして収録されることもあります。
ユージン・オーマンディ指揮フィラデルフィア管弦楽団の交響曲第3番「オルガン付き」(Sony)にオマケ収録されていた「バッカナール」は、カスタネットも入ってカラフルな演奏になっていました。
普段あまり演奏される機会のない「フェアトン」や「ヘラクレスの青年時代」、その他の管弦楽曲もまとめて聴きたい方は、優秀録音で定評のあるこちらのデッカ盤をどうぞ。
チョン・キョンファ(ヴァイオリン)による「序曲とロンド・カプリチオーソ」と「ハバネラ」も同時収録されている豪華版です。
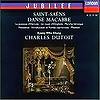 |
交響詩「死の舞踏」:サン=サーンス作品集
シャルル・デュトワ指揮
1. 交響詩「死の舞踏」 1977-80年 ステレオ録音 Decca 輸入盤 |