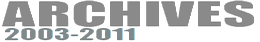果しなき流れの果に 小松左京
ハヤカワ文庫JA (1966-1973)
 |
果しなき流れの果に 小松左京
|
ジュラ紀の大地を闊歩していたティラノザウルスが、電話の呼び出し音にノイローゼになって死んでしまうプロローグが秀逸。
続く、謎の四次元砂時計をめぐるミステリーがすこぶる面白い。
次々と関係者が消えてゆき、残された野々村の恋人が、故郷でひっそりと老いてゆく姿が切なく、泣ける。
時間は更に過ぎゆき、22世紀――資料衛星に保管されていた20世紀のニホン製のテレビに、番匠谷教授の幽霊が映し出される。幽霊は何かを訴えているようだが、それを研究調査中に、資料衛星はテロリストによって爆破されてしまう。
更に時は流れ……
本当は先のエピソードよりも時間が戻っているのだけど……21世紀。
地球は終焉の時を迎えていた。
原因は太陽の不規則変動。人類の英知ではどうしようもない。
一部の人々は火星に移住したが、残された人々は、残り三時間に迫った終焉の時を覚悟して待っていた。壊れるものは壊れてしまい、自殺するものは自殺してしまい、いまは諦めるのを通り越して、虚脱したような平穏さで迎える地球の最期。
そのとき、突如現れたる謎の円盤UFO! 「あんたたち、助けてやるから、早く円盤にお乗りなさい」 かくして地球種知的生命体は、半ば強引に宇宙人に拉致されてしまう。
連れて行かれた先は、大気や構成元素が地球にそっくりの惑星。重力や太陽からの距離もまったく同じ。我々は地球の過去の時代に運ばれてしまったのではないか? 夜になって星座をみれば何もかもはっきりするだろう。
――なんてこと言ってるときに、一同は猿人に襲われ殺されてしまう。
388ページの小説の、ここまでが223ページ、全体の約半分。
そこから先の展開は……
さっぱりわからん。
ある組織が、時間移動を繰り返し、歴史を改竄しようとしている。
そして、それらの行為を阻止しようとしている組織がある。
また、それらの組織には、タクシーの車内から忽然と姿を消した野々村が一員として加わっている(らしい)。
地球終焉の際に宇宙人に拉致された松浦という男も、どちらかの一員みたいだ。
いや、よく分からないけど。
20年くらい前に読んだときも分からなかったけど、いま読み返しても、よく分からない。よく分からないけど、この作品は、小松左京の代表作で、時間テーマSFの大傑作なのであ〜る。
よく分からんのに、代表作だとか大傑作だとか、断言していいのか?
よいのであ〜る。
なぜならば……「歴史って、変えてもいいんじゃないの?」という問いかけが、とても強烈だからであ〜る。
H・G・ウェルズが1895年に『タイム・マシン』を発表して以来、「過去は変えちゃいかん」というのがSF小説の常識でした。それは「他人に迷惑をかけちゃいかん」と同じくらい頑固な考え方で、みんな、その常識に納得していたわけです。
ポール・アンダースンの『タイム・パトロール』のように、過去を変える奴、歴史を変革しようと企む奴は悪玉で、それを未然に阻止しようとするパトロール員は正義の人、みたいな取り決めが、不文律としてあったわけです。子どもの頃に見ていたSFアニメでも、同じようなルールが大前提となって作られていました。過去を変えるようなだいそれた事を考える奴は、『バック・トゥ・ザ・フューチャーPARTII』のビフのように、私利私欲のためにやっていたので、素直に悪役と決めつけていたんですね。
ところが小松左京は、この『果しなき流れの果に』で、過去を積極的に変えようとする行為を、肯定的な視点から、グイグイと読者に押しつけてくるんです。
もし、中世の時代にペニシリンがあったら、多くの人命が救えたではないか。
もし、20世紀のドイツで独裁者の誕生を阻止していたら、多くのユダヤ人が無為に殺されなくてもすんだじゃないか。
もし、有史以前の地球に21世紀の文明を持ち込んだら、人類はもっと進化発展したのではないか――そんなことを、真っ正面から、堂々と問いかけてくるんです。
凄いっす。
ストーリーが破綻していることは、小松さん自身も自覚されているようで、次のようなコメントを書かれています。
「未来」という分野のはらんでいる題材が、あまり多すぎるため、ついつい個々の作品の完成度を高めることよりも、大急ぎで、問題点をピックアップして行く、ということに重点をおくことになりました。――(略)――ほんとうのことをいえば――私にはもう、昔のような意味での「文学的完成」などということは、どうでもよくなっているのかも知れないのです。
(『神への長い道』あとがきよりの引用)
テーマの大きさ、重さ、それと「これぞSF!」と声に出したくなるような、豊富なアイディアが、この小説の魅力です
本作にはこの他にもアイディアはギュウギュウに詰まっていて、後年、長編化される『日本沈没』の話も(その後の祖国を失った日本民族の行方さえも)、この小説の背景の一部として含められています。
日本SF界の巨星の名にふさわしい、小松左京の代表作です。
よく分からんけど。 ^_^;