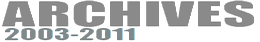ゴルディアスの結び目 小松左京
角川文庫 (1977-1980)
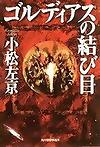 |
ゴルディアスの結び目 小松左京
|
4つの掌編によって構成された連作短編集です。
初出は角川書店の「野性時代」。
最先端科学(当時)を扱ったバリバリのハードSFが、一般小説誌に掲載されていたという事実が、70年代SFブームを象徴しています。
「加速度的に量と精度をあげていく物質、生命、人類、地球、宇宙についての、今日的情報は、私にとって、たえまなく「新生」へと生まれ変わり続けるメッセージの大シンフォニーのようなものだ。……もし「旅」が、時空間移動プラス「新しい情報との遭遇」を意味するなら、私たちは今、めくるめくばかりに壮大で高速の旅へのり出した事になる……そして、この四篇は<私自身の、「もっとも個人的な旅」の備忘録>であり、<……それぞれ「出発」「渦」「難破」「孤島」に関する、ほんの一行ずつのメモ>なのだ…………地球上には、まだこの天体が、じかに、むき出しに、「宇宙」とむかいあっている場所がいくつか残されている。……(そうした場所には)「人文史」「地球史」の一部でなく「宇宙史」の微小部分であるような、この天体の「裸の皮膚」がのこされているように感じる」
(単行本(角川書店/1977年出版)著者あとがきより引用)
この一筋縄では括れない、異様な短編集を解題するにあたって、(俺の貧弱な分析能力ではとても太刀打ちできそうにないので)著者ご本人による「あとがき」を延々と引用させていただきました。
これをヒントに、少し俺流の(幼稚な)解説を試みてみましょう。
まず目を惹くのが、「ほんの一行ずつのメモ」という表現です。
小松左京を語るとき、まず最初に出るのが「博覧強記」でしょう。宇宙とそれを形成する事象(すなわち森羅万象)に関する知識量が無限大(しかもそれぞれの分野において、最先端の情報に精通している)、という驚異であります。知らない事以外はなんでも知っている俺なんぞは、平身低頭する他に為す術(すべ)がございません。
その博学な著者が、この連作短編集では、自らの膨大な知識量に逡巡し戸惑っている、そんな印象を受けました。とにかく語るべき物語、議論すべきテーマがあまりにも巨大で、かつ多岐に渡っているため、どこから手をつけていいのか見当がつかない。当惑してしまった著者は、とりあえず書けそうな断片部分から、「ほんの一行ずつのメモ」として残すことにした……そんな創作動機を想像します。
文庫本(角川文庫版)で、各70ページの短編小説のどこが「ほんの一行ずつのメモ」なんだ、というご意見もあるでしょうが、なにしろ巨人・小松左京です。一行メモでも常人の感覚とは比較にならないくらい巨大なのです。
また、「私自身の、もっとも個人的な旅の備忘録」というフレーズは、この連作短編集の特色を端的に言い表しています。
「私自身の」「もっとも個人的な」「備忘録」……つまり、これ、私小説です。
「SFは文学ではない」と批判され、「SFは単なる文学でなどある必要はない。むしろ、文学でしかありようがないものと、根本的に違うキャパシティを持つのがSFなのだ」と、既成の文学論に反旗を翻(ひるがえ)した小松左京。その反骨の巨人が、文学王道であるところの私小説に挑戦……ということではありません。
本来自由で広大肥沃な表現手段だった文学から、あらゆる娯楽要素を拒絶したため、自己変革・発展能力を失い衰退してしまったのが純文学。その対局に位置し、SFアイディアを駆使することでしか成し得なかった文学表現の成果が、この「ゴルディアス」4部作と言えます。
但し、著者が、「自身のために」を目的として書いた小説(=私小説)なので、小松SFワールドに不案内な読者には、説明不足に感じられる部分もあると懸念されます。
では、小松左京がこの連作短編集に著した「もっとも個人的な備忘録」とはどんなものであったか、それぞれの「旅」の内容を簡単にまとめておきます。
「岬にて」(「出発」に関する一行メモ)
地球から宇宙へ向かって突きだした岬にて。ドラッグに酔い、宇宙と対話をして暮らしている人々がいる。日本から訪れた青年が俗事を話題にするが、誰も相手にしない。ここでは、地球とは異なる時間によって世界が創られているようだ。
ストーリーは青年がやってくる朝から始まって、時間がループし、青年がやってくる朝(冒頭と同じ描写)で終わる。
「ゴルディアスの結び目」(「渦」に関する一行メモ)
要塞のような病院に、マリア・Kという可憐な少女が収容されている。
鋭い牙と頭部に角状の突起物を生やした少女には、邪悪な存在が憑依しており、鉄のバンドで身体を拘束されているにもかかわらず、騒霊現象(ポルターガイスト)を起こし、病室内をメチャクチャに破壊する。
精神分析医が少女の深層心理に侵入し、"憑きもの"の正体に迫るが、病室は大音響とともに内部に向かって崩壊し、収縮しはじめた。
その理由や内部の物理的構造、一切の情報が解明されないまま、かつて「マリアの部屋」と呼ばれていた病室は収縮を続け、やがてマイクロ・ブラック・ホールへと成長してゆく。
「すぺるむ・さぴえんすの冒険」(「難破」に関する一行メモ)
お前を人類の中からただ一人えらんで、宇宙の一切の秘密と真理を教えよう。その代償に、こちらは二百二十億の全人類の生命をうばう……どうだ、お前は、この申し出を受けるか?
ミスター・Aが何度も繰り返しみていた夢、しかし目が覚めて1、2時間過ぎるとみたことさえサッパリと忘れてしまっていた夢は、ただの夢ではなく、”地球”外から直接意識に送り込まれたメッセージだった。中枢機構管理責任者は、緊急会議を招集する。しかし、そのとき”地球”は、引き返し不能な速度で、破滅へ向かって突き進んでいた。
(この作品には、叙述トリックによる状況設定が施されているため、内容の半分の側面しか書いていません)
「あなろぐ・らう゛」(「孤島」に関する一行メモ)
虚飾も羞恥も取り払い、有るがままに為すがままに、獣と化してセックスをしている若い男女。二人の凶暴なまでに激しい営みは、やがてクライマックスをむかえ、娘は快楽の絶頂に「宇宙」を出産する。
森羅万象、すべては男女のセックスによって産み出されたとする、世界中のあらゆる地域に共通して存在している神話をベースにした掌編。
「一行メモ」と言うよりも、どちらかといえば、クロッキーみたいなもので、大まかでいいところはザッと流し、肝心な部分は細部まで丁寧に描き込んでいる、そんな印象です。
とは言っても語彙の豊かさは相当なもので、昨今の芥川賞作家の(女学生の日記帳にしかみえない稚拙な)駄文なぞ、足元にも及びません。
小松左京の魅力は、「あなろぐ・らう゛」にみられるような、センチメンタリズムへと回帰してゆく、独特の倫理感覚にあります。地球が真空に浮かぶ一個の球体に過ぎないという醒めた認識を持ち合わせていながら、物語に用意された着地点がクールでドライであった例しはありません。
クスリ漬けにされセックス奴隷に貶められたマリアの悲劇(「ゴルディアスの結び目」)は、きわめて無垢で純真だった「愛」がもたらした過ちであり、情緒的で非論理的な少女の幻想(センチメンタリズム)が背景にあります。
マリアを救出すべく無謀を承知で異世界へ侵入、引き返せないことが分かると、更にその向こう側がどうなっているのか興味を持ってしまう精神分析医の行動も、科学者の探求心というより、感情的な衝動によるものでしょう。
同様のセンチメンタリズムは、「すぺるむ・さぴえんすの冒険」の主人公が最終的にくだす(地球ローカルのモラルに殉じた)判断にも見受けられます。宇宙に放射された「地球の種子」をできるだけたくさん救いだそうとする超越存在には感動させられてしまいました。(超越存在さえも、感傷的に行動してしまうんだ!)
ささやかでちっぽけな個の感情が、絶対的質量を有する知性を凌駕してしまう、そんなロジックが、小松左京のSF小説には施されています。
所詮人類というものは「論理的倫理より、情緒的・美的倫理の方がわかりやすいし、陶酔しやすい」知性体だし、世の中のあらゆる側面で(あるいは根本的部分で)どのような意識変革があろうとも、そこのところだけは変わらないであろうという認識。そんな人類に向けられた、著者の温かい眼差しが感じられる短編集です。