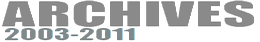ワーグナー管弦楽曲集
September 23, 2006
ヘルベルト・フォン・カラヤンが20世紀を代表する名指揮者だったことに、異論はないです。ことに1955年から音楽監督を務めたベルリン・フィルとのコンビは最強でした。
レパートリーも多彩だったし、演奏は常に最高水準の出来映え。
文句のつけようがない。つけいる隙間もない完成度です。
そういったある種の権威への反発なのか、カラヤンを否定するのが一種のステータスになると勘違いしている人も多いです。
万人が認めている巨匠を貶すって、快感ですからね。
ぼく、カラヤン嫌いなんですよ。
そんなこと言ってる人のほとんどが……ぼくは一般人とは違うんです、レベル高いんです、それくらいクラシック音楽に精通しているんです、と言下に匂わせているわけで……まあ、簡単に言ってしまえば、クラヲタの自己顕示欲。
で、カラヤンを否定して、あまり知られてない指揮者を過剰に持ち上げる。カラヤンばかりが指揮者じゃないぞ。世間にはもっと注目されてしかるべき名人は大勢いる。人気先行でカラヤンカラヤン言うな。たまには他の演奏にも耳を傾けろ……いわゆる判官贔屓ってやつ。
気持ちは分かりますけど、やり過ぎると見苦しいです。
『スター・ウォーズ』以降のジョン・ウィリアムスは好きじゃないとか、ジョン・ウィリアムズは70年代が最高だった、ブロックバスターな映画ばかり担当してるから過剰評価されているんだ……とか言ってる人も、(多分、根っこにあるのは)同じでしょう。
ジョン・ウィリアムズについては、(機会があれば)改めてまた書きます。
ところで……
貧乏性なせいか、子どものころから大人数で演奏された楽曲、つまり交響曲とか管弦楽曲のレコードばかり買っていました。
1枚1000円〜2500円を出すわけですから、なるべく多くの制作費を掛けて演奏されたレコードがいい。1枚が同じ値段なら、大編成のオーケストラ音楽の方がお得感があるじゃないですか。だから、ピアノ・ソナタとかヴァイオリン・ソナタとか、1人や2人で演奏されているレコードは、まず買わない。
(もう一つの趣味、ジャズを例外として)この貧乏嗜好は今でもそうで、器楽曲のディスクはほとんど買いません。グルダのベートヴェン・ソナタ集と、フランソワのラヴェルくらいしか持っていませんです。
ひところ内田光子のモーツァルトに夢中になって、Philipsのピアノソナタ集を買い漁ってましたけど、聴かなくなったので中古盤屋に売り払ってしまいました。
(内田光子は最高のモーツァルト弾きだと、いまでも思ってますけど)
だからオーケストラ音楽でも、室内楽より管楽器も入っている管弦楽団、2管8型より4管16型、打楽器も沢山使っていて、声楽(男女混声合唱&独唱)が加わればもっとよろしい……ってなこと言ってると、究極はマーラーってことになっちゃいます。
更にオペラだと、音楽の他にストーリーや演技も入っていて衣装や舞台美術も愉しめる。とってもゴージャス!
そこで、波瀾万丈ドラマチック超大作のワーグナー「ニーベルングの指輪」の登場となるわけですが……1話が4時間(最初のだけは2時間半)で4夜連続、入場料もバカ高くなって、貧乏人とは無縁の世界に突入してしまう諸刃の剣。
……ここで、今年の春に来日して「ニーベルングの指輪」4部作を連続公演したワレリー・ゲルギエフについて書きたいのだけど、長くなるので割愛。(もちろん見てませんが、おおむね不評だったらしいです)
まあ、ワーグナーは「リング」4部作に限らず、どれも長過ぎて少々退屈してしまいますけどね。レコード(CD)持っていても、通しで全部聴くなんてことは、買ってから1度もありません。1枚だけ聴いてみるとか、リモコン片手にぱしゃぱしゃスキップ。
普段はハイライト盤とか管弦楽曲集のような、1枚もののディスクしか聴かない。
ここまでが、本日の前フリ。
そろそろ本題に突入しますです。
ワーグナーと言えば、なんてったってこの人、このディスク。
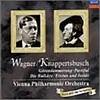 |
ワーグナー:名演集
ハンス・クナッパーツブッシュ指揮
キルステン・フラグスタート(ソプラノ) 3
1. 「神々の黄昏」夜明けとラインへの旅 1956〜1959年 ステレオ録音 Decca |
これは問答無用でしょう! 同時代に活躍していたフルトヴェングラーの管弦楽曲集(EMI)も名盤ですが、いかんせん1938年〜1954年のモノラル録音で、音質に少々難あり。
その点クナのデッカ盤は、プロデューサーのジョン・カルショウが絶対の自信を誇っていた録音技術の粋をこらした名盤。左右の拡がりと前後の奥行きが立体的に再現された、(当時の)アナログ・レコーディングとしては最高水準であります。
余談ですが……このディスク、最初にCD化されたとき(当時3000円だった!)は低域弦楽器の音がぶぉーんとこもっていて、LPの音質に大満足していた私は、「このクソ野郎!」と、普段は絶対口にしない下品な罵声を吐いて、早々中古盤屋に売り払っちゃったのでありました。
デッカ・ベスト100シリーズとして再発売された廉価盤(1000円)は、オリジナル・マスターを使ってるらしく、本来の音質に近いものになっていたので、とても嬉しく思います。「ジークフリートのラインへの旅」の旅立つ部分や「ヴォータンの告別」の冒頭など、管楽器群がぐわーんと高揚するところの迫力は素晴らしいです。
デッカ録音は、(例えばラジカセのような)安物のオーディオ装置でも、優秀な音質に聞こえるので好きです。記録されているすべての音が明瞭に聞こえる。コストパフォーマンスの高い録音と言えるでしょう。
クナのワーグナー演奏の凄いところは……とてつもなく遅くて重い。
これは是非ともカラヤンと聴き比べていただきたいところ。
カラヤンのワーグナー管弦楽曲集にはEMI盤(ベルリン・ドイツ・オペラ)とGrammophon盤(ベルリン・フィル)がありますが、おそらくほとんどの方がカラヤン盤のほうが標準というか、模範演奏というか、カタログ的というか、こちらが本来の在り方で、クナのテンポは必要以上に遅すぎると感じられるでしょう。実際遅いし。
そこのところ、クナの個性というか、体臭がぷんぷん臭ってきて、人によっては拒絶反応さえ起こしかねない。
昼飯に例えるなら……カラヤンはロイヤルホストの日替りAランチ、クナは頑固親父のとんこつラーメン。
万人が好む味ではないかも知れません。だけど好きな人にはこれが堪らなくいい。他のお店では真似できない独特の味。気に入った人はドンブリの底に残ったスープの1滴まで飲み干してしまう。
そんな感じ。
閑話休題(それはさておき)……
ストコフスキー・ベスト5、第4位の発表です。
 |
ワーグナー管弦楽曲集レオポルド・ストコフスキー指揮
シンフォニー・オブ・ジ・エア
「ニュルンベルクのマイスタージンガー」 1961年〜1974年 ステレオ録音 RCA(輸入盤) |
シンフォニー・オブ・ジ・エア(NBC交響楽団)、ロンドン交響楽団、ロイヤル・フィルハーモニー管弦楽団を指揮した、1961年〜1974年の録音。ワーグナー作品をたっぷり(79分)1枚にまとめた、超お買い得の1枚。シンフォニー・オブ・ジ・エアを指揮した「ヴァルハラ城への神々の入場」と「ヴァルキューレの騎行」は声楽入り。
これまた端正なカラヤン盤とは対照的に、テンポ揺らしまくりの熱演。
クナ盤とダブっている「ジークフリートのラインへの旅」、「ジークフリートの葬送行進曲」、「トリスタンとイゾルデ:第1幕への前奏曲」の演奏時間を比較すると……12分33秒と12分09秒、7分34秒と7分12秒、10分12秒と10分06秒。それぞれ、思っていたほど違いはないです。
クナが一貫して終始同じゆったりとしたテンポなのに対し、ストコフスキーは遅いところはより遅く、早いところはより早くやっているってことになりますでしょうか。
とにかくメリハリのつけかたが尋常じゃありません。
結果、どういう印象になるかというと、聴き手に緊張を強いるところと、緊張を開放するところが適度に出てくるので、よりリラックスして聴けるってことです。
この2枚のワーグナーを聴いた後では、カラヤン盤の味気ないこと味気ないこと。カラヤンが20世紀を代表する名指揮者だってことは、認めているんですけどね。
全国規模のファミレス・チェーンといったら大企業ですもの、個人事業主のラーメン屋の親父とは比較にならんですよ。
旨いかどうかは別問題だし、味覚は人それぞれですからね。
幾ら自分の好きな店だからって、相手の好みも知らないで(初めてのデートで)脂ギトギトのとんこつラーメンには誘えないですよ。(女の子との最初の昼飯は)無難に小綺麗なファミレスですね。絶対。
さて、本日のテーマは「官能」です。
あそれ、かんかんのおー、きゅうのですー。
「らくだ」(古典落語)じゃねえってば。
官能、せんしゅある、性的な刺激、そそる肉体的欲望、感覚的快楽の美学。
これだけはある程度の年齢を重ねて、実際に体験してみないと分からない。しかも相手のあることだし、タイミングも重要でしょう。
それを音楽で表現してしまったんだから、ワーグナーって凄いっす。
「トリスタンとイゾルデ」って物語自体が許されぬ不倫の恋(個人的に不倫って大嫌い)だけど、ストーリー抜きで音楽だけ聴いても、実に官能的なんですね。
まるで朝凪に寄せる白波。なめらかで艶めかしく、次第に熱を帯びてきて……果てる……そして余韻。
これ聴いてセックス以外のことを連想するのは、はなはだ難しい。
この楽曲は、クナ盤にもストコ盤にも入ってます。
聴き比べの感想書こうと、「第1幕への前奏曲」と「イゾルデの愛の死」ばかり何遍も繰り返し聴いていたら、悶々としてきちゃったので……
今日はこのへんで失礼します。