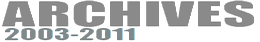今月のレコード・ライブラリー
March 20, 2010
 |
メンデルスゾーン&ブルッフ:ヴァイオリン協奏曲
アンネ=ゾフィー・ムター(ヴァイオリン)
1. メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調 作品64 1980年9月 デジタル録音 Deutsche Grammophon |
まるで近所の女子高生が、親切で優しいおじちゃんの職場に遊びに来て、ヴァイオリンの腕前披露したら、おじちゃんが「お嬢ちゃん、上手だねえ」なんて感心してるような、微笑ましくも和やかなジャケットであります。
これがどうして、数あるメンデルスゾーンのVN協奏曲のなかでも、(5指は無理としても)10指には数えてもよいくらいの名演奏。
まあ、すべてはカラヤンの掌中での出来事で終始しておりますが。
カラヤン没後のムターのスーパー・ウーマンぶりと比較して、あれこれなにやら想像しながら聴くのも一興かと。
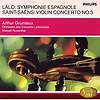 |
ラロ&サン=サーンス:ヴァイオリン協奏曲アルテュール・グリュミオー(ヴァイオリン)
1. ラロ:スペイン交響曲ニ短調 1963年4月 ステレオ録音 Philips |
フランコ・ベルギー派のヴァイオリニスト、アルテュール・グリュミオーの蠱惑の音色が魅力的な、サン=サーンスとラロのヴァイオリン協奏曲。
フランコ・ベルギー派というのは、ジプシー感覚を持ったヨーロッパ・ヴァイオリニストの流れだそうで、「ツィゴイネルワイゼン」の作曲者としても知られるサラサーテが、その代表格だとか。哀感たっぷりな歌わせかたに特徴があります。
ジュリアード出身の、巧くて美しいけれど個性を感じないヴァイオリニストが主流な現在、このタイプはめっきり見かけなくなってしまいました。
サン=サーンスもラロも、ヴァイオリンの技巧と効果、美しいメロディたっぷり。どちらもグリュミオーの独断場ですね。
粋で鯔背(いなせ)で恰好良い演奏。
63年の録音ですが、鑑賞に支障なしの音質。
日本のプロ・ヴァイオリニストや音大生に「ロン・カプ」と呼ばれているサン=サーンスの「序奏とロンド・カプリチオーソ」もオマケ収録。
ラロの「スペイン交響曲」は、第3楽章もばっちり演奏している全5楽章版。この第3楽章が、歌謡曲的メロディでいいんです。
 |
ベートーヴェン:ヴァイオリン協奏曲&ソナタ第9番ヤッシャ・ハイフェッツ(ヴァイオリン)
シャルル・ミュンシュ指揮 ボストン交響楽団 (1)
1. ヴァイオリン協奏曲ニ長調Op.61 1955年11月(1)、1960年9月(2) ステレオ録音 |
ステレオLP最初期の1955年11月録音。
録音が素晴らしいのはもちろんのこと、ハイフェッツの貫禄ある大名芸は一聴の価値有り。
パガニーニ以前のヴァイオリン協奏曲ですから、超絶技巧でリスナーを唖然とさせるような楽曲ではありません。独奏は転調を重ねながら音階を上下させるだけなのですが、ベートーヴェンらしい優しいメロディと雄大な曲想が魅力で、メン・チャイと並ぶ人気コンチェルト。膨大な数の録音盤があるなかで、やっぱりハイフェッツ盤は、頭一つ抜けた存在感がありますね。スピーディなテンポが気持ちいいです。
ミュンシュ&ボストン交響楽団の伴奏も、雄々しくってベートーヴェンにベストマッチ。
カップリングが、ベトVNソナタの最高峰「クロイツェル」ってのが嬉しいです。
 |
ベートーヴェン:ヴァイオリン・ソナタアルテュール・グリュミオー(ヴァイオリン) 1. ヴァイオリン・ソナタ第4番イ短調 1956-57年 モノラル録音 Philips |
ソナタ第5番の最初の一音から、もうすっかり春!
グリュミオーは美しい。ハスキルは優しい。
幸福感に満ちたベートーヴェンのソナタ。
1956年のモノラル録音は問題なし。
とても柔らかく美しい音質です。まんぞくまんぞく。
 |
メンデルスゾーン&チャイコフスキー:VN協奏曲アイザック・スターン(ヴァイオリン)
メンデルスゾーン:ヴァイオリン協奏曲 ホ短調
チャイコフスキー:ヴァイオリン協奏曲 ニ長調 CBS Sony ステレオ録音 |
アイザック・スターンの「メン・チャイ」。
ロシア的な荒々しい感情表現と雄大なスケール感、巨匠の貫禄に圧倒されるチャイコフスキーのヴァイオリン協奏曲。ロストロポーヴィチのシンフォニックかつエネルギッシュな伴奏も絶妙。文句なしの名盤。
メンデルスゾーンは、オーマンディ&フィラデルフィア管弦楽団と共演した1958年の演奏のほうが、華やかな緊張感があります。小澤の伴奏も見事だし、ベテランならではの余裕たっぷりなリラックスムードも渋くて、魅力ではありますが。