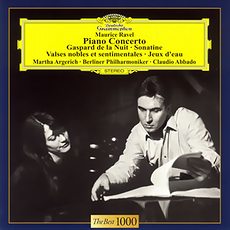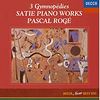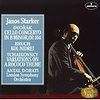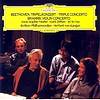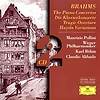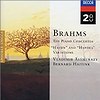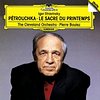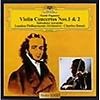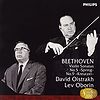ヴァイオリン協奏曲集 「四季」 作品8-1〜4
バロック時代末期のイタリア人作曲家アントニオ・ヴィバルディが書いた、日本で最も親しまれているヴァイオリン協奏曲。
「和声と創意への試み」と題された12のヴァイオリン協奏曲集(作品8)のなかの最初の1〜4集で、各曲は急−緩−急の3楽章で構成。
自由な楽想の独奏と、同じ楽想を反復する総奏が交互に現れるリトルネルロ形式が、4つの協奏曲に統一感をもたらしています。
4つの協奏曲には、それぞれ「春」「夏」「秋」「冬」の標題があります。
これは作曲家によって命名されたものではなく、楽譜の冒頭に書かれていた、四季の風景を描いたソネット(14行詩)より連想されたニックネームです。
作曲年代:1720年ごろ(モルツィン伯ヴェンツェスラウに献呈)
楽譜出版:1725年、アムステルダムのル・セーヌ社より出版
「和声と創意への試み」と題された12の協奏曲集(2巻の分冊)
楽器編成:独奏ヴァイオリン、第1・2ヴァイオリン、ヴィオラ、通奏低音(チェロ・コントラバス・チェンバロ)
楽曲構成:
第1曲:協奏曲第1番 ホ長調 作品8−1(RV269)「春」
第1楽章 アレグロ ホ長調 4分の4拍子
春が来た。小鳥のさえずりは春の挨拶。
そよ風に誘われて、小川はせせらぎの音をたてる。
黒雲に稲妻が走り、雷鳴が春の到来を告げる。
嵐がおさまると、小鳥たちは再び歌いだす。
第2楽章 ラルゴ 嬰ハ短調 3分の4拍子
花咲き乱れる牧場にて。
木々の青葉がそよぎ、山羊飼いはうたた寝している。
第3楽章 アレグロ ホ長調 12分の8拍子
羊飼いと妖精たちは、春の陽射しのなかで一緒になって
笛の音に合わせて踊り回っている。
第2曲:協奏曲第2番 ト短調 作品8−2(RV315)「夏」
第1楽章 アレグロ・ノン・モルト ト短調 3分の8拍子
灼けつく太陽の季節。
人は疲れ、家畜も倒れ、木々も枯れる。
カッコウが鳴き、爽やかな涼風が吹くが、
冷たい北風が、にわか雨を降らせて、羊飼いは嘆く。
第2楽章 アダージョ−プレスト ト短調 4分の4拍子
羊飼いは恐れと不安に疲れ果てる。
稲妻が走り、雷鳴がとどろく。
周囲を、群をなした蠅が、煩く飛び交っている!
第3楽章 プレスト ト短調 3分の4拍子
雷鳴と落雷の脅威。
雹が降り、麦の穂をなぎ倒す。
第3曲:協奏曲第3番 ヘ長調 作品8−3(RV293)「秋」
第1楽章 アレグロ ヘ長調 4分の4拍子
秋の収穫を祝う村人たち。
歌と踊り、浴びるようにワインを飲み、祭りは賑わう。
第2楽章 アダージョ・モルト ニ短調 3分の4拍子
宴のあとに、静寂がやってくる。
村人たちは平穏な眠りに誘われる。
第3楽章 アレグロ ヘ長調 3分の8拍子
夜明け。
角笛を携えた狩人たちが、犬を連れて狩に出かける。
逃げる獲物、追う狩人。
獣は、追われ、追いつめられ、力尽き果てて、息絶える。
第4曲:協奏曲第4番 ヘ短調 作品8−4(RV297)「冬」
第1楽章 アレグロ・ノン・モルト ヘ短調 4分の4拍子
冷たい雪と風の中を、身を縮めて足踏みする。
厳しい寒さに、歯の根が合わずカタカタ鳴る。
第2楽章 ラルゴ 変ホ長調 4分の4拍子
囲炉裏端にて、暖かい、幸福なひとときを過ごす。
窓の外は冷たい雨。
しかしそれは、やがて新しき生命をもたらす、恵みの雨。
第3楽章 アレグロ ヘ長調 3分の8拍子
転ばぬよう用心深く、氷の上を歩く。
滑って、転んで、起きあがって。
再び、氷の上を歩く。
ひっくり返って転んだら、今度は氷が割れた。
扉を開いて、風の音に耳をすます。
こうやって春の兆しを待つのも、冬の楽しみのひとつ。
演奏時間:約45分
この時代の楽譜は、簡素な記譜法で書かれているので、演奏者の解釈によってかなり様子が違ってきます。
特に近年は、バロック音楽の研究家が監修にあたったオリジナル楽器演奏盤が主流だとか。
まずは、オーソドックスな、スタンダード&ベストセラー・ディスクから。
 |
ヴィヴァルディ:合奏協奏曲集「四季」
ピーナ・カルミレッリ(ヴァイオリン独奏)
1. 合奏協奏曲集「四季」第1番 ホ長調 「春」 1982年 デジタル録音 (Philips) |
ヴィヴァルディの「四季」といえば、イ・ムジチの「四季」。
最初のベストセラーはフェリックス・アーヨ(独奏ヴァイオリン)による1959年録音盤(Philips)でした。徹底したレガート奏法で肉太の音色。春の訪れを喜ぶ覇気に満ちたリズム感覚。指揮者を置かない自発的なアンサンブルも見事。イ・ムジチで選ぶなら、まず最初に挙がるディスクですが、やっぱり少々古さを感じる音質です。
そこで、次善の盤として、ピーナ・カルミレッリ(独奏ヴァイオリン)による1982年デジタル録音盤をご紹介。楽団初の女性首席奏者(コンサートミストレス)による優秀録音盤です。独自解釈の即興演奏もなく、ひたすらオーソドックスでありながら、流麗で明るく、いつ聴いても新鮮な表情をもっています。
あとイ・ムジチでは、1969年録音のロベルト・ミケルッチ独奏盤(Philips)も甲乙つけがたい名盤。
つまり早い話が、イ・ムジチならハズレなし、どれもいいです。
お好みのジャケット・デザインと懐具合でお選びください。
イ・ムジチの演奏で、保守本流、オーソドックスかつスタンダードなヴィヴァルディに馴染んだところで、
次に聴いていただきたいのが、ネヴィル・マリナー指揮アカデミー・オブ・セント・マーティン・イン・ザ・フィールズ(アカデミー室内管弦楽団)の演奏。
 |
ヴィヴァルディ:協奏曲集「四季」
アラン・ラヴディ(ヴァイオリン)
1. 協奏曲集「四季」 1969年 ステレオ録音 Decca |
マリナー盤は冒険編。通奏低音にオルガンを加えチェンバロと使い分けていたり、装飾音符も少々過剰。いろいろ変わったことをやっていますが、足が地に着いており、奇を衒ったオチャラケ演奏ではありません。日本でマリナーの名を知らしめた記念碑的名盤。このディスクを聴いて、「四季」はイ・ムジチだけではないことに気づかされた人は、多いんじゃないかしら(私もその中の一人)。「四季」に既成概念を強くお持ちの方ほど、よりたくさん楽しめます。
 |
ヴィヴァルディ:協奏曲集「四季」
ニコラウス・アーノンクール 指揮
1. 協奏曲集「四季」 1976年 ステレオ録音 Teldec |
バロック時代の古楽器を使った演奏盤からも1枚。アーノンクール&ウィーン・コンツェントゥス・ムジクスによる1976年録音盤。18世紀の楽器は、モダン楽器に比べてピッチが低いから音色が違うのは当然として、クレシェンド/デクレシェンドを排したハードボイルド・スタイル。キビキビしい。ヴァイオリン独奏はアリス夫人。
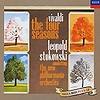 |
ヴィヴァルディ:協奏曲集「四季」
1. ヴィヴァルディ:協奏曲集「四季」
2. バード:ソールズベリー伯爵のパヴァーンとガリアード Decca |
ストコフスキー&ニュー・フィルハーモニア管弦楽団のデッカ・フェイズ4録音盤は、この指揮者ならではのスペキュタラー巨編。
小編成で演奏されることが当たり前なヴィヴァルディの「四季」に、(たぶん12型か14型の)分厚いオケを起用、それを充分に機能させて、まるでロマン派後期の交響詩の如き絢爛豪華サウンドを演出。
ライナーノート(平林直哉氏)によれば、この演奏は「基本的に楽譜通りの演奏である」そうです。とてもそうは聞こえないけど、そういうことらしいです。ホンマカイナ? と疑いたくなるけど、「基本的に楽譜通りの演奏である」と書いてあるのだから、そうなんでしょう。上記に並べた演奏盤とは、(メロディ以外は)絶対に別の曲に聞こえるけど。
「春」「夏」「秋」「冬」の詩(ソネット)に順応した、交響詩的解釈。
とにかく、オーケストラをゴージャスに鳴らすことにかけて、ストコフスキーの右に(左にも上にも、斜めにも)出る者なし。余人を寄せ付けないストコ爺の独断場であります。
最後に言い訳:
えー、ベスト3なのに今回は4枚紹介してしまいました。
結局のところ、ヴィヴァルディの「四季」は、録音盤の数だけ異なった演奏があり、それぞれに面白味もあるので、極端な話、10枚でも20枚でも、興味のあるもの、好きなソリスト、贔屓の指揮者・楽団のディスクを、片っ端から買って聴いてくださいってことです。
聴き比べこそ、ディスクで音楽を聴く醍醐味であります。
10枚の「四季」を聴き比べて、この独奏者はどうだこうだ、この楽章のテンポはあれよりこっちの方が適切だとか、蘊蓄垂れるようになったらあなたも立派なクラシック・ファン。クラ・ヲタと呼ばれる日も近いです。