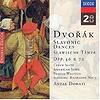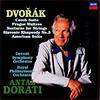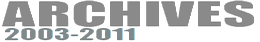「のだめカンタービレ」Lesson1:ドヴォルザーク
April 17, 2007
テレビドラマ版「のだめカンタービレ」は、音大ピアノ科の学生・千秋真一が幼少のころ過ごした、プラハでの回想から始まります。
「なぜ僕は、ここにいなければならないんでしょうか?」
冒頭のモノローグ、いいですね。
自分の居場所を見失っている青年が、仲間たちと出会い交流のなかで成長し、人生に希望と目的を見出すまでの物語。
作品のテーマが、最初からキチンと提示されています。
このプロローグ、原作の漫画にはなかったらしいのですが、こんなところに脚本家の実力が発揮されますね。
前回、伏線の貼りかた、状況設定や人物設定が出鱈目と書きましたけど、脚本家はドラマのセオリーをちゃんと把握している人のようなので、ずいぶん悩まれたんじゃないかなって、(勝手に)想像しちゃいますね。
分かってるのに変えられないジレンマ。
それはさておき……プラハです。
なぜプラハと分かったのかと言うと、画面にプラハとテロップ出たからで、私にはヨーロッパの街なんて何処も同じに見えますから、なければプラハだと分かりません。
プラハと言えば、フィリップ・カウフマン監督の『存在の耐えられない軽さ』という映画がありました。1969年のチェコ動乱(プラハの春)を背景に、男女関係をじっくりと描いた出来の良いメロドラマでした。ダニエル・デイ=ルイスとか、けっこう人気がありましたけど、スコセッシの『ギャング・オブ・ニューヨーク』以来、とんとご無沙汰ですね。
最近は、舞台中心に仕事しているのかしら?
このダニエル・デイ=ルイスという英国の役者さん、二枚目ではあるんですけど、どことなくエキゾチックなルックスなんですね。母親はユダヤ系の女優さん。父親はアイルランド出身の詩人です。
このお父さん、セシル・デイ・ルイスの人生が面白いんです。
アイルランドで牧師の息子として生まれ、オックスフォード大に進み、大学教授の職に就くのですが、左翼活動家として追放され、しかたなく売文屋として収入を得ているうちにソビエト共産主義が受け入れられなくなり、今度は英国諜報部に入って、女王陛下から勲章まで貰っているんです。まさに波瀾万丈の人生です。
で、大学を放逐された失意の時代(1938年)に、生活のために書いた娯楽小説が、復讐ものの傑作『野獣死すべし』。
そうなんです、ニコラス・ブレイクは、詩人セシル・デイ・ルイスが売文屋として使っていたペンネームだったんですよ!
そんなことはどうでもいいのですが……
「のだめカンタービレ」第1回の冒頭(回想シーン)、その背景に流れる音楽には、びっくりさせられましたね。
なんといっても舞台はチェコですから、ここはドヴォルザークかスメタナで決まりでしょう。
直感的にスメタナの「モルダウ」とか……安易に貼り付けてしまいそうなものです。
それでノープロブレム。なにも問題はない。いいじゃん「モルダウ」で。
ところが……このドラマの選曲、演出家かプロデューサーか、または音楽担当の服部さんか、誰が決定権を持っていたか知りませんが、かなり凝ったことやってくれます。
いかにもチェコ国民楽派らしいオーケストラ曲。
パッと聞いて、ドヴォルザークっぽいんですが、曲名は分からない。
有名な交響曲第7番〜第9番でないことは確か。
第1番〜第6番はあまり聴いたことないので、たぶんその中のどれかかな?……なんて考えながら調べてみたら……なんと「チェコ組曲」。
みなさん、この曲ご存知でしゅか〜?
よくまあ、こんなマイナーな曲を探してきたものです。
ドヴォルザークは、1882〜85年に、序曲「フス教徒」など一連の愛国的な作品を書いていますが、「フス教徒」の作品番号は67で、「チェコ組曲」の作品番号はもっと若くて39……なので、有名な「弦楽セレナード」(op.22)と「管楽セレナード」(op.44)の間、たぶん1879年前後、ドヴォルザークが37歳ごろに作曲した曲だと思います。
数年前に出ていた数枚の国内盤CDは、すべて廃盤。
アマゾンを検索して、ようやく適当な輸入盤が見つかりました。
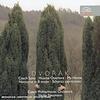 |
ドヴォルザーク:「チェコ組曲」、他
ヴァーツラフ・ノイマン 指揮
同時収録: Supraphon(輸入盤) |
録音盤の選択肢が少ないから、仕方ありません。「のだめ」でにわかクラシック通になった方は、こちらをお求めください。
聴いたことないけど、郷土料理に定評のあるノイマン&チェコ・フィルの演奏ですから、大はずれってことはまずないでしょう。
とにかく、このドラマを見ているとクラシック音楽が好きになってくるから不思議です。
登場人物たちが劇中で演奏する曲ばかりでなく、劇伴として流用された楽曲さえCDを買い揃えたくなる。
そんな方々のために、流用元となったSony音源をつまみ食いしたコンピレーション盤もリリースされていますが、どうせならブツ切れよりもちゃんと全曲収録されたものを、名盤として定評のあるCDを揃えたい。
かと言って、あれもこれも買っていたのでは、狭い我が家がますます狭くなる。
CDなんて意識してなくても、どんどん増え続けますからね。
例えば4畳半と6畳の2DKのアパートを5万で借りたとします。(計算が面倒くさいので、台所・浴室・便所・玄関などの付帯設備は考慮に入れないことにして)1畳あたり月4762円の家賃を払っていることになります。
最初は100枚、200枚と増えてゆく枚数に満足の笑みを浮かべていたものの、1000枚を越えたあたりから数えるという行為の虚しさを実感。本人の意思を超越して増え続けるCDに部屋は足の踏み場をなくし、4畳半は居間としての機能を停止、倉庫化してしまうと……月21428円がCDのための家賃になります。年間だと約25万7千円!
ろくに聴きもしない、1年に1回聴くか聴かないかのCDのために、年間25万7千円も支払い続ければならないなんて、バカバカしいじゃありませんか!
21世紀の科学技術を導入して、CD音源をパソコンのハードディスクに圧縮保存する方法もありますが……何枚あるか分からないCDを全部デジタル化する手間は、ちょっと考えただけで思考停止、そんな面倒なことやってられっか世界に突入。
なにより保存用HDDを増設する銭があるのなら、1枚でも多くCDを買いたいのが素直な気持ち。でなければ、居住空間を圧迫するほどの脅威には到っておりませんです。
ということで、音源デジタル化案はあっさり却下。
そこでやはり、戒律というか掟が必要となってくるわけです。
ルールのないところに文化は育ちません。
是々非々でやらねば、CD蒐集は収拾がつかなくなります。
(ただ駄洒落が言ってみたかっただけ。深い意味はない)
で、次回は……CD購入の掟について書きます。