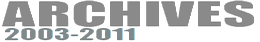「のだめカンタービレ」Lesson1:ベートーヴェンのピアノソナタ
April 23, 2007
「おれは、こんなところで何をやってるんだ。クソッ!」
自分の居場所を見失っている千秋真一が、焦燥感に駆られて弾くのは、ベートーヴェンのピアノソナタ第14番「月光」の第3楽章。
そして、エリート専門にレッスンしている江藤先生の教室を馘になった千秋が、聞こえてきたピアノにふと足を止め、「これじゃ「悲愴」じゃなくて、「悲惨」だな」と嗤う場面は、ピアノソナタ第8番「悲愴」の第2楽章。
ベートーヴェンの人気ピアノ曲、2連打。
毎度「のだめカンタービレ」ばかりで、どうもすみません。
興味ない方には、ほんとにどうでもいい話題ですもんね。
それに……「のだめ」で使用された音楽を、こう細かく書いていたんじゃ、なかなか先に進みませんね。
いやそれよりもっと切実なのは、CDがどんどん増えて、身動きとれなくなっちゃいそうです。
そこで、超個人的にしばりと言うかルールと言うか、CD購入の掟(おきて)を作ってみました。
掟(おきて)・その1「名盤しか買わない」
クラシック音楽の同曲異演盤は、ポピュラー音楽のそれとは比較にならないくらい多い。比例して駄盤も多いと思います。
駄盤蒐集も面白いですけどね。
駄盤の山で部屋の床を沈めちゃって、「お〜ま〜え〜は〜あ〜ほ〜か〜」とか、関西弁で嗤われるのは癪に障るし。
というか、自己嫌悪で自殺したくなるだろうし。
名盤とされているディスクを、全部聴いてるわけでもないので、まずは名盤にターゲットを絞って買いましょう、ということです。
野放しにしておくと、聴くことよりも集めることを優先しちゃう性格なので、この際、駄盤蒐集の愉しみは放棄しちゃった方がいいのです、私の場合。
問題は、なにを以て「名盤」と認定するか? ですが……
普通に、音楽評論家が褒めてるディスクでよろしいのじゃないかと。
聴いている絶対量が桁違いだし、銭を貰って原稿書いている人たちだから、素人の感想文よりは信憑性があるでしょう。通販サイトのカスタマーレビューとか、ぜんぜんアテになりませんからね。
但し、評論家とて人間だから機嫌の良いときと悪いときがあるだろうし、嗜好の方向性はそれぞれですから。なるべく多くのご意見を参考にさせていただいて。
ストコフスキーとか、バーンスタインの「ラプソディー・イン・ブルー」とか、私の愛聴盤を褒めている人なら、まあ方向が同じだから間違いは少ないんじゃないかと。
そういう先生のご意見を優先しちゃおうかと。
掟(おきて)・その2「発売後10年を経過したCDしか買わない」
プロの評論家先生というのは、新しい録音には点が甘いんです。
別名・業界の寄生虫ですから、レコード会社に媚びを売るのは当然といえば当然。安い廉価の再発売盤より、価格の高い新しいディスクを話題にしたほうが、レコード会社にウケがよい。
ライナーノートの原稿依頼も増えます。
新譜を貶すなんて、お得意様に喧嘩を売ってるようなものです。
賢いオトナは、(いや別に賢くなくても、普通に)そんな愚行は避けますよ。常識として。
新聞文化面のディスク・レビューなんてのは、そのもっともたるものですね。
そんな業界の寄生虫でも、もともと音楽が好きな人たちばかりなので、リリースされてから数年経過すると、本音が出てくるんですね。
発売時にベタ褒めしていたディスクも、話題にしなくなる。まるでそんなCDはこの世に存在しなかったのように、冷酷に無視する。
別に擁護するわけじゃないですけど、発売された時点で斬新であったものが、歳月とともに色褪せてしまうのはよくあることです。
だからといって、一般消費者の私が、そんなのに踊らされても、一文の得にもなりゃしない。踊り損。時間の無駄。疲れるだけ。
本当に良いものはいつの時代になっても残るし、メッキはいつかは剥がれるものです。ただ私は「のだめ」の影響で音楽に興味を持った「にわかクラシック・マニア」なので、何がメッキで何が本物なのかを見分ける鑑識能力がない。だから発売されて間もない新譜には手を出さない、ってことです。
つまり、他人が既に普遍的な評価を出しているディスクしか買わない。
自分だけの名盤探しを放棄します。
それなくしてどうするの。個人の趣味なんだから、他人に迷惑をかけない範囲で、好きなものを好きなときに好きなだけ聴けばいいじゃない。もっと冒険しなさいよ。
そんな声も聞こえてきそうですが……もう私には、冒険心なんてありません。歳も歳ですし、冒険しても年寄りの冷や水と嗤われるだけです。個人の趣味なんだから、私の勝手です。私の好きなようにさせてください。
掟(おきて)・その3「聴き比べをしない」
同曲異演盤の聴き比べは、とても楽しいのですが……これをやり始めるとキリがない。
それに結局最終的に、聴くのはいつも同じディスクに限られてしまうので、時間と銭の無駄になります。「のだめ」の影響で音楽に興味を持った「にわかクラシック・マニア」のすることじゃありません。
とりあえず1曲1枚。じっくり聴き込むこと。これだけはしっかり胸に叩き込んでおかねば。
掟(おきて)・その4「1000円以下のCDしか買わない」
クラシックの老舗レーベル、デッカ、グラモフォン、フィリップスを擁するユニヴァーサル・ミュージックが、海外輸入盤(というか裏青海賊盤やら不法ネット配信)への対抗策として、過去の名盤を一斉に1000円廉価盤でリリースしました。
日本コロムビアやワーナー・ミュージックも、1000円廉価盤を出しています。
ソニー・クラシカルは、以前からオーマンディ&フィラデルフィアなどを1000円で出していましたが、本家とBMGが合併したため、海外では旧RCAレーベルの音源をBMG Sonyがリリース開始(輸入盤は1000円程度で国内販売されている)。
その危機感から、廉価盤価格を1500円にしていたBMGジャパンも、昨年の暮れに「シャルル・ミュンシュの芸術」シリーズ全40タイトルを、1000円(2枚組は2000円)で発売しました。
東芝EMIの廉価盤価格は1300円。先月までは3枚買えば1枚無料キャンペーンをやっていて、これだと4枚で1000円以下になるけど、送料350円だし、抱き合わせ商法はやっぱりセコい。EMI音源なら2枚組のフランス盤が1300円くらいで買えるし、本家EMIからライセンスを買い取ったブリリアント盤なら2枚組でも1000円以下。東芝EMIにはもう少し頑張って欲しい。
レコード業界の価格破壊王として騒がれたナクソスでさえも、もはや特別安いレーベルとは思われなくなっているのが現状なんです。
そんな時代に、CD1枚1000円以上払う気になれないのは、当然でしょう。
私は貧乏人特別指定の個人事業主だから、その気持ちが強い。CD購入を必要経費として落とせるディレクターや音効さんの3千倍強い。気持ちの単位が馬力なら、たぶん100万馬力くらい強い。
国内盤は1000円以下、海外輸入盤はそれ以下でなきゃ買わない。
(買えない)
掟(おきて)・その5「モーツァルトは買わない」
昨年(2006年)は、モーツァルト生誕250年記念ということで、巷(ちまた)にはモーツァルトが溢れていました。ウィーンのみならず、国内コンサートでもよくプログラムされていたし、ラジオやテレビもモーツァルトだらけ。
モーツァルトかベートーヴェンか、どちらか一つを選べと問われれば、850MHzの素早さで「モーツァルト!」と答えるくらい好きですが、かなり食傷気味です。
新しく買わなくったって、けっこうCD持ってるし。買わずに済むのなら、それで済ませたい。CDをたくさん買ったからという理由で勲章を貰った人は、(たぶん)いません。
モーツァルトにプロポーズされたこともあるマリー・アントワネットは言いました。「パンがなければケーキを食べればいいじゃない」
モーツァルトは買わなくても、ベートーヴェンを買いますから。
それで許してください。
そんな5つの掟(おきて)を妄想してみましたが……
さて、実践できるかどうか?
とりあえず、今回は……
ベートーヴェンのピアノソナタ第8番「悲愴」と第14番「月光」。
幸い、この2曲は数あるベートーヴェンのピアノソナタのなかでも屈指の人気曲でありまして、ほとんどのCDはこの2曲と、第23番「熱情」をカップリングしてリリースされてます。
人気曲だけあって名盤と称されているCDも多いです。
ベートーヴェンのPソナタくらい、決定盤認定でもめる曲はないのでは?
アシュケナージが良い。いやブレンデルだろう。グルダが最高。グルダはクセが有りすぎ、リヒテルが一番だ。なにを言うかベートーヴェンはバックハウスのモノラル盤に限る。ポリーニの名前が挙がらないのは、個人的な恨みでもあるのか? ここでグールドとか言ってみるテスト。グールド厨 キタ━━━━━━(゜∀゜)━━━━━━!!!!! とか……
今回、私が選んだ推薦盤はこちら。1000円盤です。
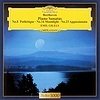 |
ベートーヴェン:ピアノソナタ 「悲愴」「月光」「熱情」エミール・ギレリス(ピアノ)
1. ピアノ・ソナタ 第8番 ハ短調 作品13 「悲愴」
1980年 デジタル録音(1,2) |
第8番「悲愴」は、ベートーヴェンの初期を代表するピアノ曲。
伝統的なピアノソナタにない革新的な点が多くみられるので、ロマン派ピアノ書法の原点とされているそうです。
なるほどモーツァルトのPソナタと比べれば、より感情的な表現がいっぱい入っています。「月光」や「熱情」のように、後年、他人が付けたニックネームと違って、「悲愴」は作曲家本人が付けた標題ですし、なにか特別な思い入れがあったのでしょう。
このベートーヴェンという作曲家、それまでのやり方を壊すのが好きだったらしく、いろんな分野で(当時としては)アヴァンギャルドなことを、いっぱいやってます。
第14番「月光」は、それまで常識だった「第1楽章はアレグロにきまっておる」を覆して、第1楽章からいきなり緩徐楽章(アダージョ・ソステヌート)です。
このピアノソナタは、第13番と合わせて「幻想曲風ソナタ」(作品27)として発表されたので、13〜14番と続けて演奏されることを前提に、第1楽章のアレグロを省略したのかも知れません。そうじゃないかも知れません。なにしろ「のだめ」の影響でクラシック・マニアになった奴の言うことですので、私の考察には信憑性がまったくありません。
右手の三連符でタタタ、タタタ、タタタと伴奏される第1楽章が超有名ですが、「月光」っぽい情景を連想させるのは、この第1楽章のみ。
レルシュタープって詩人が、この第1楽章を聴いた印象を、「スイスのルツェルン湖の月光の波に揺らぐ小舟のようである」とか描写しちゃったので、いつの間にか「月光」と呼ばれるようになったとか。
第2楽章は、フランツ・リストが「二つの深淵の間に咲く花」と形容したように、可憐で愛らしいアグレット。第3楽章は、焦燥感に駆られた千秋真一が感情むき出しでガンガン弾くにふさわしい、激烈なフィナーレ。
千秋が自分の演奏を第三者の耳で聴いたら、たぶんこんなセリフが……「これじゃ「月光」じゃなくて「激昂」だな」
ところで……翌朝、のだめの演奏する「悲愴」の第2楽章を聴いて目覚めた千秋が、「カプリチオーソ・カンタービレ、気ままに気まぐれに、歌うように」と説明してますが……私の持っているCDは、すべて「アダージョ・カンタービレ(ゆるやかに歌うように)」となっています。
あれは、千秋が、のだめの演奏の印象を語っているのか?
それにしては、気ままに気まぐれには、ぜんぜん聞こえないぞ。
原作の漫画家さんも、いちおうは調べたうえで、それでも、あえてカプリチオーソ・カンタービレと言わせたかったとは思うけど……ドラマでも嘘はダメよ法案が可決されたら、放送禁止になっちゃうよ。