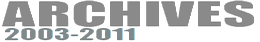「のだめカンタービレ」Lesson1:メンデルスゾーン
April 21, 2007
回想シーンが終わって、次は音大に通う千秋真一の登校場面。
「ヘタクソ……ドヘタクソ……みんなヘタクソ……」
心の中で悪態をつきながら、校庭を歩く千秋真一。
学生たちが校舎の窓から顔をのぞかせ、千秋のプロフィールについて、あれこれとお喋りしています。
このやり方は「聞いたか坊主」といって、シナリオの基本中の基本。
往来に立てられた看板に町人たちが群がっていて、坊さんが「怪盗ねずみ小僧、捕らえた者には金五十両と書いてある」などと説明し、町人たちが、各々、「鍋島様の武家屋敷に入るとはふとい野郎だ」「でも盗まれても困らないような、金持ちの家にしか入らないらしいよ」「盗んだ金は貧乏人にバラ蒔いてるんだってさ」「いまどき珍しい義賊だねえ」「けっこうな色男だって噂だよ」みたいな話をしていると……そこに本人が通りかかるという、超古典的脚本術。
昔は字を読める人は限られていたし、諸国を旅している修行僧なら事情通だし、アウトラインを説明するのに最もふさわしい人物だったということでしょう。
モノローグやナレーションで本人に延々喋らせるより、もっと立体的に手際よく説明できるし、脇役(のだめの友人や、ヴァイオリンの峰龍太郎、ティンパニの奥山真澄)の顔見せも同時進行で出来るので、現在でもよく使われてますね。
デヴィッド・リーン監督の『アラビアのロレンス』も同じ手法を使ったオープニングでしたが、外国ではどんな呼び方をしているでしょう?
そんなことはどうでもいいのですが……
音大の校庭って、あんな風に学生さんたちが、授業の合間に各々練習していたりするものなんでしょうか? 面白そうですね。
行ったことないので、今度覗いてみようかしら。
いや、それもどうでもよくって……
なにが言いたいのかというと、
この場面のバックに使用されているのが、メンデルスゾーンの交響曲第4番「イタリア」の第1楽章。
フェリックス・メンデルスゾーンは、20歳になったとき、3年がかりでヨーロッパ周遊の旅に出ています。
旅する作曲家といえば、人生の3分の1を旅で費やしたというモーツァルトが有名ですが、こちらは売り込みと職探しが目的の、生活がかかった旅。
メンデルスゾーンは、諸国の文化と歴史を学び、各国の文化人たちとの交流を目的とした、純粋に教養娯楽としての旅であります。
メンデルスゾーンの一家は、ベルリンの一等地に屋敷をかまえ、しかも自宅の中には100人以上収容できるコンサート・ホールがあって、毎週著名人を招いて演奏会を催していたほどの大金持ち。
目隠ししてピアノ弾いたり、親子でヴァイオリンを弾たり、猿回し芸で貴族に媚びを売っていたモーツァルト一家とは、家柄が違います。
普通だったらそれ聞いただけで、「ケッ、ユダヤの金貸し野郎め」「苦労知らずのお坊ちゃん芸に興味ねえよッ」とか、唾棄しちゃいますけど……メンデルスゾーンの音楽には、ブルジョア的高慢な気取りが、全く感じられないんですね。
優美かつ華麗でありなから明朗快活、そしてフレンドリー。
金持ちの嫌みったらしさは、微塵もありません。
世の中には仮想敵を作らないとやる気が出ないという人や国がいっぱいありますけど、メンデルスゾーンみたいな人もいたってことだけは、知っておいて欲しいと思います。
私はメンデルスゾーンを聴くと、金持ち喧嘩せず、ってことわざを思い出しますですよ。
交響曲第4番「イタリア」は、欧州周遊旅行から帰ったメンデルスゾーンが、イタリアでの印象をスケッチしておいたものを、後年ロンドン・フィルハーモニック協会からの依頼により作曲した交響曲。
初演は1833年5月13日でしたが、作曲家本人は出来に満足できず、その後もずっと改訂し続けていたとのこと。
楽譜は死後4年経ったあとに、遺作の19番として出版。交響曲第3番「スコットランド」(op.56)よりも先に作られているのに、作品番号が90番なのは、そういう理由があるからだそうです。
ちなみに現在のオーケストラが演奏しているのは、1838年6月18日にロンドンで演奏された改訂2版だとか。
明るく躍動的な交響曲第4番「イタリア」の第1楽章は、校庭を颯爽と歩く千秋にぴったり。
暗めの回想場面のあとだけに、爽やかさ抜群。
このように既成曲がドンピシャで使われたりすると、スタンリー・キューブリックの気持ちも、分からないでもないです。
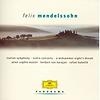 |
メンデルスゾーン作品集 DGパノラマ・シリーズ
ヘルベルト・フォン・カラヤン指揮 (1,2,3)
1. 序曲「フィンガルの洞窟」 Deutsche Grammophon |
交響曲第4番イ長調「イタリア」と序曲「フィンガルの洞窟」は、カラヤン&ベルリン・フィル。ヴァイオリン協奏曲は独奏者にムターをむかえたカラヤン&ベルリン・フィル。これだけで1500円の元がとれます。
更にクーベリック&バイエルン放送交響楽団の「真夏の夜の夢」がカップリングされ、バレンボイムの「無言歌集」からの抜粋4曲とアカデミー室内アンサンブルの「八重奏曲」の豪華おまけ付き。
デビューしたばかりのアンネ=ゾフィー・ムター(当時17歳)とカラヤン&ベルリン・フィルのVN協奏曲、クーベリックの「真夏の夜の夢」は名盤の定番。
てっとり早くお手軽にメンデルスゾーンの全体像が掴める好企画盤。オススメです。
上記カラヤンも悪くはないのですが、古くから「イタリアン・シンフォニー」の決定的名盤とされてきたのは、トスカニーニの1954年録音盤(RCA)ですね。
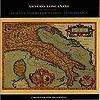 |
メンデルスゾーン:交響曲第4番「イタリア」
アルトゥーロ・トスカニーニ 指揮
1. 交響曲第4番 イ長調「イタリア」 RCA(BMG JAPAN) 1954年 モノラル録音 |
久しぶりに聴いたら、スケールの大きさ、風格、熱狂的な迫力。
これを凌ぐ演奏は、残念ながらステレオ盤には見当たりません。
CD化で音質も改善されているので、モノラル録音にアレルギーのない方には、このトスカニーニ盤が絶対のオススメです。